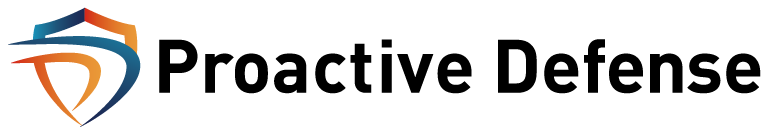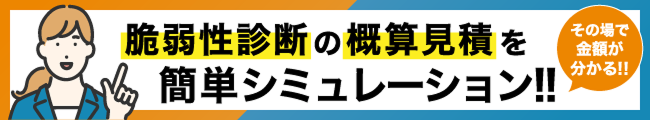量子コンピュータの進化が、私たちの暮らしに革新をもたらす時代が近づいています。創薬や診断支援といった医療分野でもその可能性に大きな期待が寄せられる一方で、医療セキュリティの観点からは新たなリスクが指摘されています。なかでも懸念されているのが、量子コンピュータによって従来の暗号技術が無力化される可能性です。
医療機関では、電子カルテや医療IoT機器の通信、保険情報のやり取りなど、日常的に扱う機密情報が多いです。これらの機密情報が将来的にまとめて解読されるリスクが現実味を帯びてきています。
【前編】である、本記事では、量子コンピュータが医療セキュリティにもたらす脅威についてわかりやすく解説するとともに、いまから実施すべき対策についてご紹介します。【後編】では、前編の解説を元にした、実務的な対策について解説します。
第1章 医療データと量子コンピュータの脅威
冒頭でも触れた将来的に解読する「今盗み、将来解読する(Harvest Now, Decrypt Later)」、いわゆるハーベスト攻撃が懸念されています。本章ではなぜ医療分野でハーベスト攻撃が懸念されているのか、その理由を解説します。
1.患者情報の長期保護の重要性
医療情報は他分野と比べても機密保持期間が長く、患者の個人健康データは数十年以上にわたり保護する必要があります。
例えば未成年者の医療記録は120年以上の機密保持が求められるケースもあり、量子コンピュータがその期間内に実用化される可能性は十分高いとされています。また、医療データには氏名や生年月日から診断・疾患情報まで含まれ、その漏洩は患者のプライバシーや安全に深刻な影響を及ぼします。
こうした長期にわたるデータ保護の必要性から、将来的に現在の暗号技術が破られるリスクを無視できません。
2.ハーベスト攻撃と将来の漏洩リスク
攻撃者が通信や保管されている暗号化データをいま蓄積し、将来量子コンピュータによって一斉に解読しようとするハーベスト攻撃が現実味を帯びています。特に近年は膨大な医療情報がオンラインで扱われており、これらが将来まとめて解読されれば大規模なプライバシー侵害につながりかねません。

「量子コンピュータが実用化するまで時間がある」と思いがちですが、専門家はその登場が数十年単位で迫っていると見ています。対策準備には長いリードタイムが必要ですので、医療機関は量子計算時代を見据え、早い段階からリスク低減策に着手することが求められます。
第2章 耐量子暗号(PQC)と医療業界の動向
量子コンピュータ時代に備える新しい暗号技術として「耐量子暗号(PQC: Post-Quantum Cryptography)」が国際的に標準化されつつあります。ここではPQCの基本と標準化の進展、および医療分野への影響について述べます。
医療業界固有の規制や指針におけるPQCへの言及状況を確認し、医療機関が対応すべき最新動向を整理します。

PQC標準化の進展
現在、米国国立標準技術研究所(NIST)を中心に次世代暗号標準の策定が進んでおり、2024年には耐量子暗号としてCRYSTALS-Kyber(鍵共有)、CRYSTALS-Dilithium(デジタル署名)、SPHINCS+(ハッシュベース署名)といったアルゴリズムが連邦情報処理規格(FIPS)として正式承認されました。これらPQCアルゴリズムは今後各種製品やプロトコルに実装され、将来の暗号基盤を支えるものとなります。医療を含む厳格な規制業界でも例外ではなく、これら新標準がセキュリティ確保の土台になると期待されています。
一方、日本国内でもCRYPTREC(暗号技術評価プロジェクト)によって2023年に調査報告書が公開され、2024年度版の耐量子暗号ガイドラインが策定されるなど、標準化動向の共有と検討が進められています。
業界横断的な標準は整備されつつあり、医療分野もその潮流を注視する必要があります。
医療業界における規制と期待
医療分野では、データや機器の長寿命ゆえに早期から暗号の将来対応を計画することが望まれます。
例えば米国食品医薬品局(FDA)は2023年の医療機器サイバーセキュリティ指針で、「製品ライフサイクルを通じてセキュリティ機能が有効性を保つこと」を求めており、具体的には強力な暗号アルゴリズムの採用や将来のアルゴリズム更新を可能にする設計(暗号のアジリティ)を義務付けています。
現時点でPQCの実装自体は要求されていませんが、耐用年数が長い機器ほど将来的な暗号の進化(PQCへの移行)を見据えた計画が必要とされています。このように海外では規制当局が将来を見越した対応を促し始めています。一方、日本国内の医療に関する明確なガイドラインはまだ多くありませんが、個人情報保護や情報セキュリティの既存規制の延長線上で、量子耐性を備えた暗号への移行がいずれ求められると考えられます。
医療機関側でも自主的に最新標準や政府動向をウォッチし、先手の対応戦略を立てることが重要です。
第3章 医療現場特有の課題
耐量子暗号への移行は一筋縄ではいきません。医療現場には他業界にはない独自の制約や課題が存在します。ここでは、病院・診療所がPQC対応を進める上で直面しがちな技術的・組織的課題を整理します。
レガシーシステムと医療機器の制約
多くの医療機関では長年使われている電子カルテシステムや医療機器が稼働しており、暗号アルゴリズムの変更やアップデートが容易でないケースがあります。医療機器は一度認証・承認を得るとサイバーセキュリティ更新のために頻繁に改変することが難しく、しかも長期にわたり使用されることが一般的です。
さらにIoT化した機器(例:遠隔モニタリングデバイスなど)はハードウェア資源に制約があり計算負荷の高い新暗号を後付けしにくい上、アップデートにも手間がかかるため、量子コンピュータに対する脆弱性が大きい分野と想定されます。このようなレガシー環境との互換性や性能面の問題から、PQC実装には技術的ハードルが存在します。
例えば、新しい耐量子アルゴリズムは鍵長や計算量が従来より大きく、既存システム上で速度低下やメモリ不足を招く可能性があります。そのため、機器・システムごとにアップグレードや最適化が必要となり、医療現場の通常業務と両立させつつ段階的に進めるような計画が求められます。
予算・人材・運用上の課題
サイバーセキュリティ対策に割ける予算や専門人材が限られている点も医療機関の課題です。
他の産業に比べITセキュリティ投資が潤沢でない病院も多く、量子対応のためのシステム更新や新機器導入にはコスト面のハードルがあります。また、耐量子暗号自体が新しい分野であり、知見を持つ人材やベンダーがまだ少ないのが現状です。社内に専門知識が乏しい場合、外部のセキュリティベンダーやコンサルタントの力を借りる必要が出てくるでしょう。
さらに、医療機関では患者ケアが最優先のため、システムのアップデートによるサービス停止時間を極力減らす必要があります。クリティカルなシステムを止めずに暗号移行を進めるには、入念な計画とテスト、段階的な展開が必須です。これら予算・人材・運用の観点でハードルを認識し、経営層の理解と支援を得ながら計画立案することが肝要です。
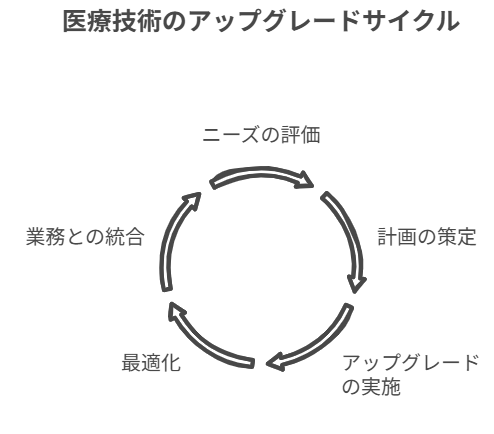
まとめ
量子コンピュータの進化は、医療業界に革新的な可能性をもたらす一方で、従来のセキュリティ基盤を揺るがす深刻なリスクもはらんでいます。特に、患者情報や医療機器の通信に依存する現代医療にとっては、量子時代の到来までに「新たな脅威への備え」を本格的に検討する必要があるでしょう。
医療業界は法規制・システムの更新制限・人材不足など、固有のセキュリティ課題を抱えており、量子コンピュータによるリスクは他業種以上に深刻化する恐れがあります。
後編では、このような状況をふまえ、医療機関が今から取り組むべき具体的なセキュリティ対策や移行ステップについてご紹介します。